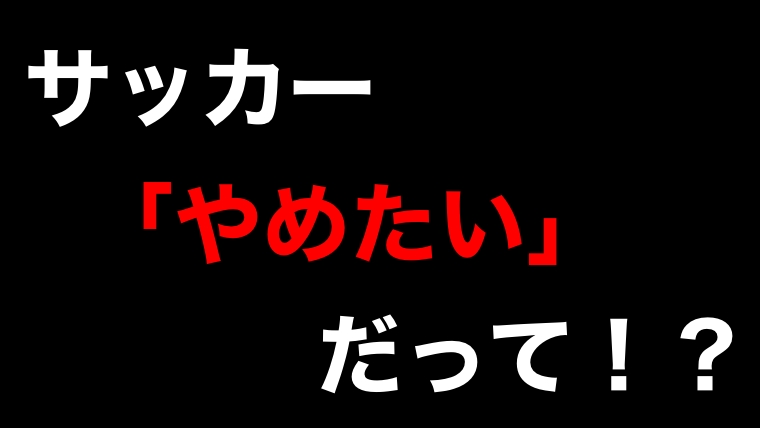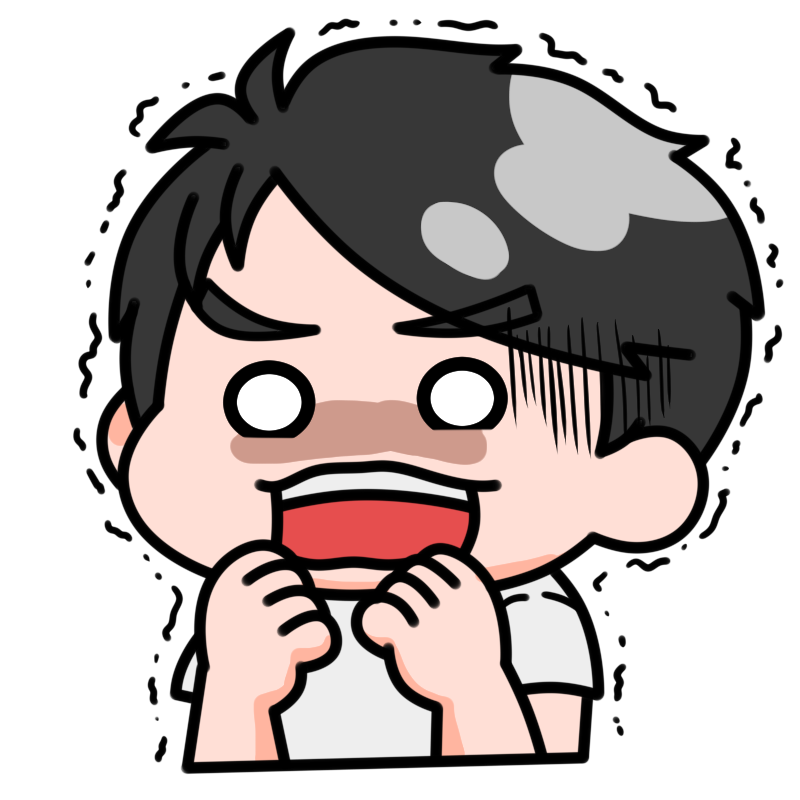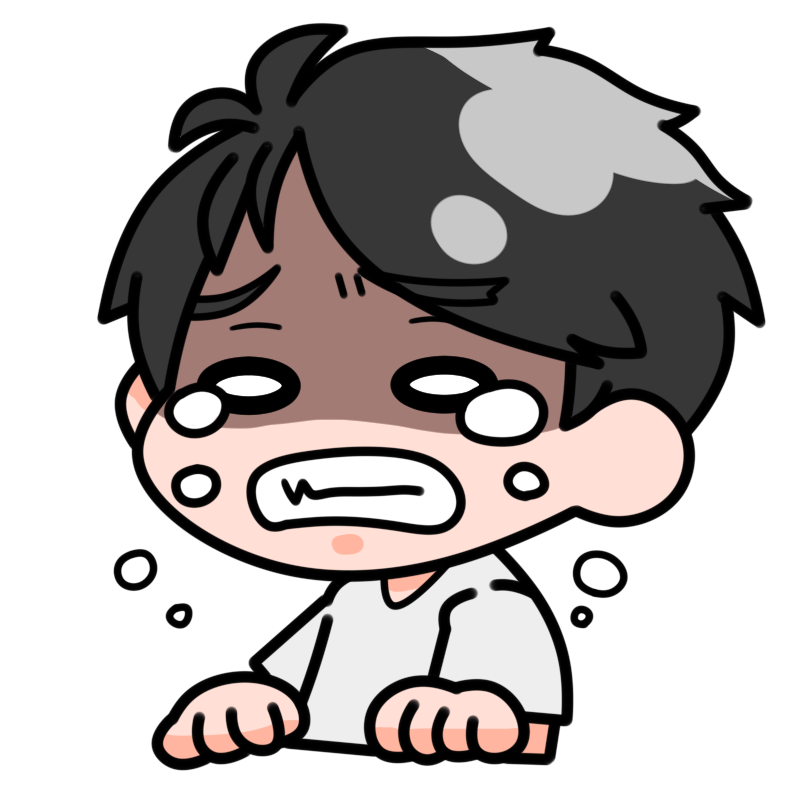小学校2年生の息子に、先日いきなり「サッカーやめたい」と言われたざわわです。こんにちは!
子どもに習い事をやめたいと言われて、頭ごなしに否定した経験はありますか?
大人としては、絶対に続けた方がいいというのが分かっているため、反射的に「ダメ!」と言ってしまいますよね。
しかし「やめたい」と言いだしたときこそ、子どもの本音に向き合い、やる気を引き出す大きなチャンスでもあります。
なぜならその言葉の裏には子どもの本心が隠れていて、そこを親が一緒に整理してあげることでモチベーションを大きく刺激できるからです。
本記事では、息子にサッカーをやめたいと言われた体験談から、子どもとの向き合い方について考えていきます!
子どもが習い事をやめたいと言いだしたら、あなたならどうしますか?
「もし自分なら?」と想像しながら読んでもらえると、嬉しいです!
息子が習い事のサッカーをやめたいと言い出した!

私の息子は小学校2年生。
1年生からサッカーのクラブチームに所属しています。
どう見ても、チームで一番下手です(笑)
ゲーム形式の練習になると、自分より年下の入ってきたばかりの子たちよりも役に立っていません…
それでも、リフティングの目標50回を達成し、ボール扱いや足の速さも向上。
楽しみながら上達しているなと感じていました。
しかし、そんなとき突然
お父さん、僕サッカーやめたい
と言いだしたのです!!
とにかく否定せずに聞いてみた
言われた瞬間、頭が真っ白になりました。
「え?なんで?」と少し威圧的に言ってしまったかもしれません…
そのせいか、「でもお父さんは怒ると思うから、やっぱりいいや…」となってしまいました。
しかし彼自身の人生であり、選択の主体が親の意思であってはならないと日々思っています。
親の気持ち押し付けるのではなく、できるだけ息子の気持ちを引き出すように聞いてみました。
怒らないから大丈夫。どうしたの?サッカーおもしろくない?
やめたい理由は?
違う。サッカーやめて習い事は体操だけにしたい。ダメ?
やめても大丈夫だよ。でもどうしてサッカーやめたいの?
…僕、みんなの役に立てないから。1つ年上の子に使えないって言われた
あ~、本心はこれですか。
以前から、すぐ年上の子にボールを渡してしまう傾向があり、理由を聞くと「年上の子に怒られるから」と言っていたのです。
そのネガティブな気持ちの積み重ねと「使えない」という暴言でやめたい気持ちが大きくなったのが原因のようですね。
息子の現状を踏まえて、親の考えを丁寧に伝えた
団体競技ではよくあることで私自身も経験があるため、すごく共感してしまいました(笑)
そっかー。それはつらいこと言われたね。お父さんもね、よく言われたんだよ・・。でもさ、まだ始めたばかりなのだから、使えない、上手じゃないのは当たり前じゃない?
うーん、確かに…
それにあなたなんて3月生まれで、ただでさえ年上の子と差があるから、当然のことだよ?
運動能力だって、小学校の低学年のうちは1年違うだけですごい差があるんだよ?
あとさ、あなたはできない子に暴言を言う子じゃなくて、できない子を励ます側になりなさい!そのほうがカッコイイよ?
そう伝えると、息子の返答に驚きました。
僕。やっぱりがんばる!
とりあえず考えてみる感じになるのかな?と予想していたのですが、まさかの答えでした。
「やめるかどうかは自分で決めていい」と伝える姿勢が、子ども自身のやる気を引き出すことにつながったのだと思います。
自分で選ぶことで、主体的な気持ちが芽生えるからです。
今回のように子どもの本音を聞き尊重する姿勢こそが、成長のきっかけとモチベーションを生むチャンスとなるのです。
サッカーをやめたいと言いだした息子の変化は?
話し合いが終わった後、息子はリビングでボールを蹴りだしました。
21時近くなっていて、もう寝る時間だよって言ってるのに(笑)
その後の彼は、チーム練習が終わった後に
僕、もう少し練習していきたい!
と言うことが増えました。
自分から練習すると言いだすことなど一度もなかったので、すごい変化ですよね!
しっかり彼の考えを聞かずに否定していたら、モチベーションはかなり下がっていたかもしれないですし、本当に良かったなと感じています。
今回の経験から得た5つの学び

今回の出来事から感じた、子どもが習い事をやめたいと言いだす前にできる心構えを5つあげておきます。
- 子どもの考えていることを丁寧に聞いてあげる
⇒親の正論や期待を先にぶつけてしまうと、子どもは本音を言えなくなります。まずは「聞く」が先です - 子どもの決断を尊重する
⇒納得感のない「続けさせられた」経験は、やる気や自信の低下にもつながります。選択の主体は子どもであるべきです - 習い事は「やめてもいい」という選択肢を持っておく
⇒「やめても大丈夫」と思えていると親自身も穏やかな気持ちで子どもに接することができます。余裕があると、子どもも安心できます - 「いい子」にさせるのではなく「自立できる大人」になってもらうよう接する
⇒「いい子」の延長線上に、自立できる大人がいるとは限りません。長い目で見て、子どもが自分の意志で選び、行動できるような関わり方を心がけたいものです - 親も反省し、子どもと一緒に成長していく気持ちを持つ!
⇒親だって完璧じゃない。自分の価値観を疑いながら、子どものペースに合わせて一緒に学んでいける親でありたいものです
「やめたい」は、単なる投げやりな言葉ではなく、子どもなりのサインです。
そこに真正面から向き合うことができれば、親子の信頼関係はさらに深まり、子どもの成長の大きなきっかけにもなります。
親として大切なのは、「続けさせること」ではなく「納得して前に進める状態をつくること」かもしれませんね。
最後に、子どもが「習い事をやめたい」と言いだしたとき、あなたはどうしましたか?
その後どうなったか私も知りたいので、ぜひコメントで教えてください!